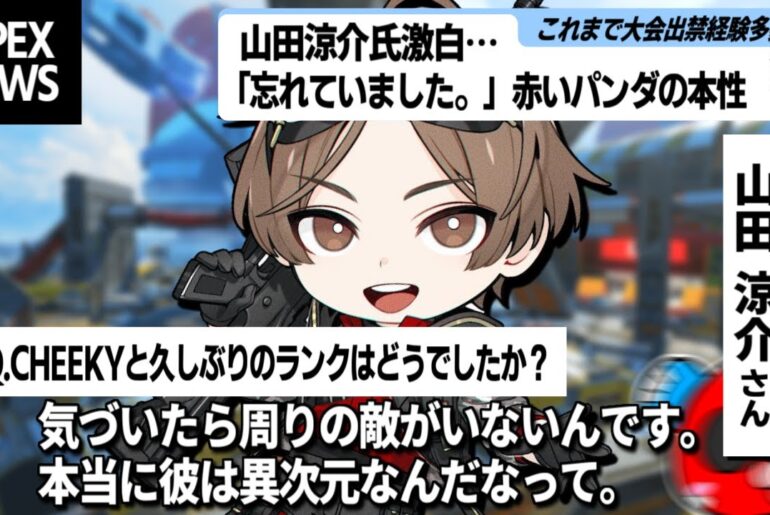歌う死神⑤
「なんだよ、その上から目線の態度は」と彼はその女の子みたいに細い腕で私の右手を掴んできたが、全く痛くなかった。
「じゃあいいですよ」と腹をくくった私は即座に言った。
「え、何?」と少年は少し驚いた顔で言った。
「だから私は直樹さんのセックス奴隷になってもいいですよ」と私は何でもないことのように言った。
「・・・・・・」と”お客”は押し黙って私を睨んでいた。
「本当は看護と中国語を教えるために来たんですけどね。“セックス奴隷”でもなんでもいいですよ。お金さえもらえれば」と私は言って、自分からブラウスのボタンを外していった。白いブラの一部が見えて、”お客”は目を見開いて凝視していたが
「いや、さっきのは冗談だよ」と”お客”は疲れた声でいって、もうお腹いっぱいというように右手を私の前で左右に揺らした。
「早くそっちも服脱いで下さいよ、何でもしてあげますよ。私とても“口”上手ですよ」と私はサディスティックな気分で怯える少年のズボンのベルトに手をかける。
「も、もう、い、いいよ、冗談だから。ちょっとビビらしたかっただけだよ」と彼が少女のように真っ赤な顔で懇願して言うので、私は手を離した。
「・・・・・・そうですか。残念です」と私は年上女の余裕を見せつけてゆっくりとブラウスのボタンをとめていく。
「何なのこの“糞チャイニーズ”」と彼がズボンを直しながら小声で言ったのを私は聞き逃さなかった。”耳”はとてもいいのだ。奴の尻を蹴りたくなったが、蹴ったら骨が折れそうだったので我慢した。私は少し疲れて、部屋の中央を占める大きなソファーに座った。”お客”は部屋の隅にある馬鹿でかい冷蔵庫からオレンジジュースを二つのグラスにいれてテーブルに置いた。
「どうぞ、飲みなよ。チンハーイーベイ チェンジー(オレンジジュースをどうぞ)」と彼は綺麗な発音で言った。
「シェシェ。中国語上手いですねえ」と私は驚いていった。そのイントネーションの正確さに驚く。
「自分でも勉強しているんだよ。学校に行ってないから時間は腐るほどあるし」と彼は少し照れくさそうに言った。
「何で中国語なんか勉強しようと思うんですか」と私はようやくまともな会話を”お客”と始められたことに安堵して言った。
「うちの芸能事務所も、これからはアジアに進出していくことになりそうなんだ。将来親父の手伝いする時に俺が中国語を話せたら、役立つだろうからね」と”お客”は意外に真面目な口調で言ったので私はびっくりしてしまった。
「すごい、・・・・・・まともなんですね」と私は驚いていった。
「悪かったなあ」と彼はまた不貞腐れそうになったので、私はあわてて
「とても偉いですね。誇っていいですよ」と私はおだてるように言った。年下の男の子は面倒だなと思いながら。でも全てはお金のためだと私は自分に言い聞かせた。ここで中国に帰ったら、公安の地獄のような取調べがまっているかもしれない。それに較べたらなんでもなかった。
3
予想以上に”お客”は熱心に中国語を勉強する。そして時々熱心にやりすぎて、熱を出したりする。そういう時私は彼をベッドに寝かしつけて、冷たいタオルで額を冷やしてあげる。そして熱を測ったり、汗を拭いてあげたり、食事時にはお粥を食べさせたりする(お粥はお屋敷に住み込みの年老いた男性の料理人が作る)。
今までの私の仕事は“お客”たちがこの世を消え去るのを待つことだったが、今回はまるで違う。この仕事の場合、何が職務の成功で、何が職務の終了を意味するか分からない。まあ給料さえちゃんともらえれば、そんなことはどうでもいいのだけれど。湖畔の施設で2年間働いて、親の借金は完済できていた。あとはこれからの自分の人生のために、稼がなければならない。日本円を母国に持ち帰れば、ものすごい価値があるのは知っていた。だから私は出来るだけこの島で”お客”の世話をして、日本円を貯めようと決めていた。その後のことは、なるようになれという気分だった。
「中国語と英語の文法って似ているようで、違うよなあ。関係代名詞の使い方とかがさあ」とベッドの中でも”お客”は中国語の文法について質問してきた。彼が言うとおり中国語の文法は日本語より英語に近いが、関係代名詞の使い方には大きな違いがある。”お客”は飲み込みが早く、教えがいは結構ある。
「そんなことはどうでもいいから、ゆっくり休んだほうがいいですよ」と私はお客がまた高熱を出さないか心配で彼に言った。
「こんなに病気ばっかりで格好悪いよね」と”お客”は無念そうにベッドの上で瞳を閉じた。
「しょうがないでしょう。誰でも運不運はありますよ」と私は”お客”を慰める。調子が悪い時の”お客”は一日中寝ていることがある。痩せてやつれている姿は結構痛ましく、私は幼いうちからずうっと病気と付き合ってきた”お客”の人生を想像してみた。しかし、どんな過酷な状況でも食事が美味しく食べられる私には自分が病気の状態というのがとても想像ができない。”お客”が眠ってしまうと、私は暇なのでお屋敷を散歩することにして彼の部屋から外に向かった。
庭に出てみると”お客”のもう一人の家庭教師である川越さんに出会った。40代前半の眼鏡をかけたちょっと小太りのおばさんで、元中学校の先生だということだ。なかなかお喋り好きで、なんでも学級崩壊がストレスで辞めたということを、聞きもしないのに初対面で教えてくれた。彼女は”お客”に国語、数学、歴史、科学、英語などを教えている。つまり中国語以外の主要科目全部だ。
「いい天気ですねえ」と私は川越さんに声をかける。彼女も”お客”が急に熱を出したので、することがないのだろう。彼女は庭の籐椅子に座って新聞をつまらなさそうに読んでいた。そこは大きな桜の木の下で、初夏の強い日差しから逃れ、気持ちの良い海からの風を楽しむには最適な場所だった。
「どう、だいぶ直樹さんと仲良くなった?」と川越さんは言いながら、私に隣の椅子に座るよう勧めてくれた。
「どうですかねえ」と私は曖昧に応えた。日本語は本当に意味をぼかして返事が出来るからとても便利だと感じた。“そうですねえ”、“まあまあですねえ”“どうですかねえ”。これらの日本語を私は好んで使った。そういうフレーズは、白黒をはっきりつける中国語にはない曖昧さがあって大好きだ。
「直樹君のお父さんはすっごい資産家だから、一人息子の彼と結婚したら勝ち組よ」と彼女はニヤニヤしながら言った。
「勝ち組ってなんですか?」言葉の意味が分からなくて私は訊いてみた。
「勝ち組ってのは、成功者ってことよ」と少し下品な笑みを浮かべて川越さんが言った。
「直樹さんとですかあ、まだ子供ですからねえ」と私は曖昧に笑った。
「何よ、折角いってあげたのに、可愛いから余裕よねえ」と川越さんは年甲斐もなく興奮する。
「……ところで、川越さんはこの島の人ですか」と私は話題を変えたくて質問してみた。
「こんな不便な島に住んでいるはずないじゃない。私は別の町から通っているのよ。毎日大橋通って」と彼女はつまらなそうにして言った。島には大きな橋があって、島の外から来る場合たいていその大橋からやってくる。また島には有名な水族館があって、週末には県内や県外から結構観光客が大橋を渡ってやってくるのだ。
「ところで、あなた本当にアイドルの玲に似ているわねえ。親戚なのお?」と彼女は私の顔を穴があくほど私の顔を凝視しながら言った。多分私を隣に座らせて訊きたかったのはこのことだろう。
「いえ、完全に他人です。私は中国人ですから」と私は迷惑に思ったが、顔には出さなかった。
「私、最初にあんた紹介された時、玲も中国人かと思ったくらいよ」
「確かに似てますねえ。私もポスター見てびっくりしました」と私は苦笑いしていった。
「玲は実は直樹さんの学校の同級生だったって知っている?」と、ものすごい秘密を告げるように彼女は鼻の穴を膨らませて興奮した顔で言った。
「え、そうなんですか」と私も驚いた顔をしてみる。本当はどうでもいいのだけど。
「直樹さんのお誕生パーティーに来ていた玲を偶然見かけた彼のお父さんが自分の事務所にスカウトしたらしいのよ」と川越さんは得意満面に言った。
「へえええ」と私は大声で言った。驚かないと失礼かと思ったのだ。
「もしかしたら、直樹さん玲のことが好きだったかもね。今じゃあアイドルで手が届かないから寧さんで我慢しようとか考えてたりして」と川越さんはまるで、自分自身が玲に似ているかのように一人で興奮しているのが、馬鹿馬鹿しく笑えた。
「はあ、代わりですかあ……それもいいですねえ」と私は苦笑いした。結構いいアイデアだと思った。すくなくとも食うには困らないだろうから。